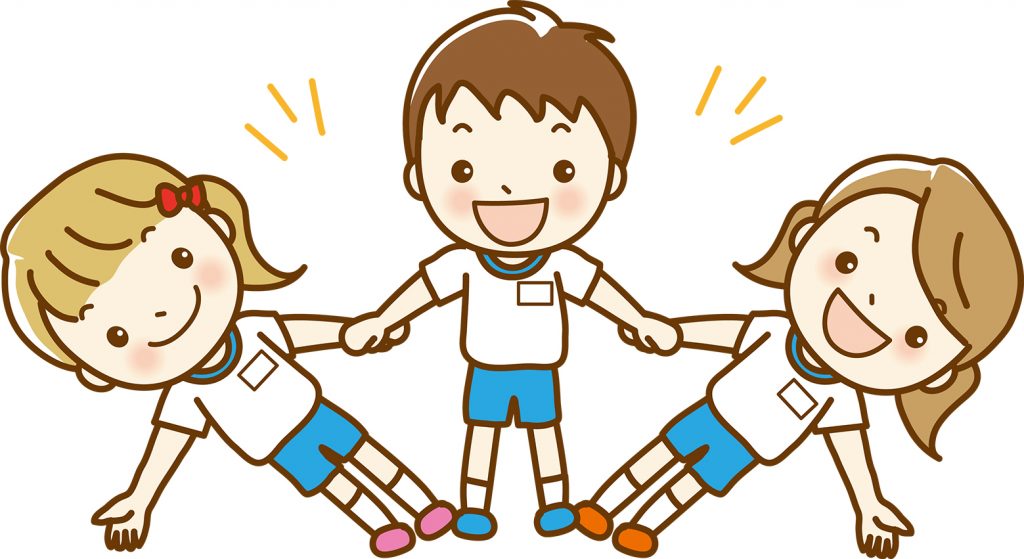
こんにちは、カメラマンhayatobellです。学校写真を10年ほど撮影しております。
今回は、組体操の撮影についてです。安全面や怪我の心配の面から「組体操をやめろ!」とか、廃止や禁止の動きがある一方、幼稚園で積極的に取り入れている場合もあります。もちろん、男子も女子も同様にです。小学校より上の学校の方が慎重になっているかも知れません。
カメラ設定
- 撮影モード:シャッター速度優先(キャノンならTv)
- 絞り:F8~F11くらい
- シャッタースピード:1/200~1/500くらい
- ISO感度:~400くらいまで
- WB:オート or 太陽光
- AFモード:ワンショット(キャノンならOne shot)
- 記録画質:JPEG M
- ストロボ:状況による
撮影モードは、運動会のデフォルトであるシャッター速度優先です。動きが少ないので、絞り優先でもいいかも知れませんが、ブレた写真を排除するのと、他と設定を合わせる目的でシャッター速度優先にしています。ブレないスキルがある方は、絞り優先でもいいかも知れません。
上記の設定で、シャッタースピードは、1/200以上で1/500くらい、絞りはF8からF11、もしくはF14くらいまでになるよにISO感度を合わせます。順光、逆光、日向、日陰など様々な場面を撮影する必要があるので、設定はこまめに変更する必要があります。
ホワイトバランス(WB)はオートもしくは太陽光です。依頼元や他の撮影内容によって変更しましょう。オートでも問題はないかと思いますが、後の編集を考えると太陽光などで一定の値にしておいた方が無難です。
AFモードはワンショットです。組体操は基本的に動きのあるものではないため、こちらで撮影します。測距点(ピントを合わせる点)は一点にして、その都度変更して合わせる方がいいと思います。自信のない方はエリアでもいいかも知れませんが、想定外の場所にピントが合わないように注意しましょう。
記録画質は、Lサイズプリントを想定しているならJPEG MもしくはSサイズでOKだと思います。
ストロボは基本的に使いませんが、最後の方で大型ピラミッドや塔などができて、下から大空バックに撮影したいときには、あった方がいいと思います。
事前準備と撮影位置

- 演技内容(特に、最後のフォーメーション)
- 最初は全面、途中から中に入り込んでいく
まずは、演技内容を確認しておきます。特に、一番最後の内容と位置取り(フォーメーション)です。塔やピラミッドならいくつできるのか、本部を向くのか、観客側を向くのか。それとも、中央に集まって、本部を向くのか、などです。
要は最後の決めショットを確実に撮るために、カメラマンはどこから撮ればいいのかを考えます。そして、最後を撮りつつも、ギリギリまで撮影枚数を稼げる導線も考えておきます。
組体操では、最初は1人、2人、3人から始まり、5人、10人と増えていくパターンが多いです。人数が少ない演技の場合は、定位置から望遠レンズと標準レンズを使って、とにかくたくさん撮ります。なぜなら、子どもたちも移動が多いため、中に入ってしまうと邪魔をしてしまう可能性があるからです。
だんだんと人数の多い縁起になってくると、隙間ができてきます。様子を見て中に入って撮影します。ピラミッドなど近くから低い位置から撮影した方が子どもたちの顔が見えて、迫力のある写真が撮れます。
撮り方
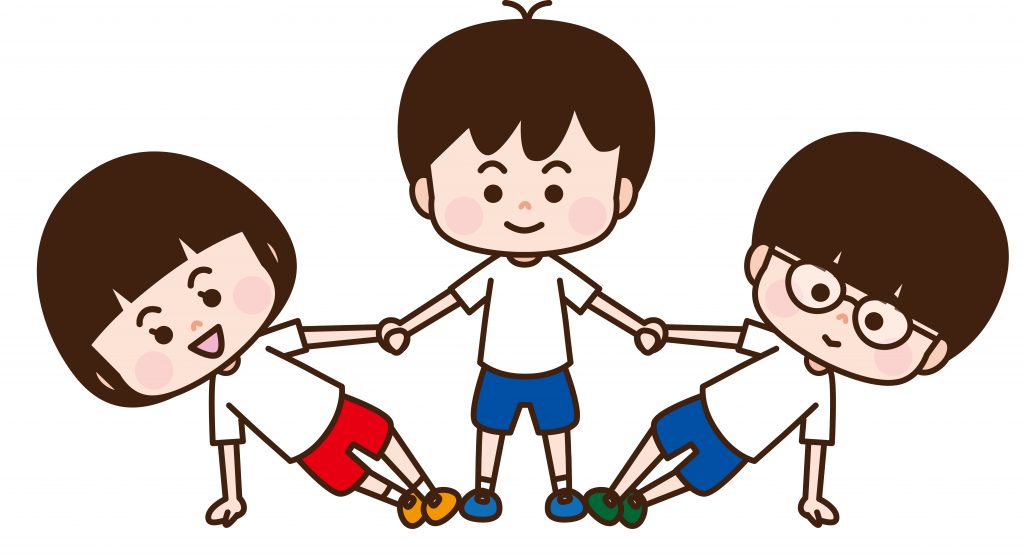
- 最初は定位置
- 途中から中に入る
- 一番最後は少し引いて全体を撮る
上記でも書きましたが、最初は定位置で撮影をして、途中から中に入って撮影します。最後は、全体が入るように引いて撮影をします。
定位置での撮影は、基本的に本部が真ん中にある場合はそこから撮影します。保護者席になっている場合は、保護者の邪魔にならずに撮影できる場所を探します。
定位置での撮影は、標準レンズで近場の子どもを撮って、望遠レンズで距離のある子どもを撮影します。完成してからの決めポーズはあっと言う間に終わってしまいますので、途中の状態から撮影します。
端から撮っていっても、途中でフォーメーションが変わってしまうと、分からなくなってしまう場合もありますが、めげずに、まんべんなく撮影するよう、努力しましょう。
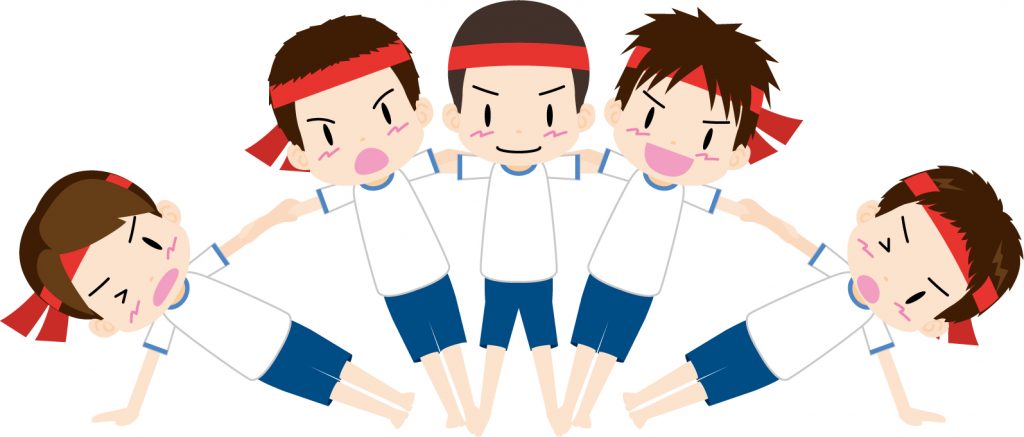
5人とか10人とか、ある程度の大人数になってきて、子どもたちの間に隙間ができて来たら、中に入って撮影します。
「すごい縁起したよ!」と言えるような迫力ある写真が撮れると、いいと思います。そのために、下の位置から見上げるような写真を撮るのがいいと思います。短時間であっちこっち走り回って、しゃがんで低い位置から撮影するのは、結構大変ですが、可能な限り頑張っていきましょう。
上記が難しい場合には、望遠レンズを駆使してできるだけ低い位置から撮影する方法もあります。この場合、正面もしくは本部の位置を向いていくれるのは、それぞれが外側の観客席を向くのかで、対応が違ってきます。後者の場合、この方法では子どもたちの顔が撮れないので、注意です。
最後は、少し引いて全体を撮ります。ピラミッドなら正面から全体を入れます。塔が複数できる場合は、一番上の子どもが向いている方向から撮影をします。それぞれ別の方向を向いている場合もあるので注意です。
ただし、一番上の子どもがポーズを決めている時間は一瞬なので、とりあえず撮って、余裕があれば正面にまわる感じがいいと思います。
卒業アルバムに使えそうなカッコいい写真が撮れるといいですね。
注意事項

- 素早く撮る
- 保護者の邪魔にならない
- 先生のサポートの邪魔をしない
- 子どもたちの安全
販売用の写真なら、素早く、数多く、全員を撮るイメージが必要です。そのために素早く撮ります。中に入って撮影する場合でも、いつまでもその場所に留まらず、素早く撮影して、移動することが大切だと思います。特に幼稚園児や小学校低学年の子どもは小さいので、カメラマンが前にいると見えなくなってしまいます

上記でも書きましたが、保護者の邪魔にならないことが大切です。組体操は花形演技なので保護者も気合の入ったカメラを構えていることがあります。写真を買ってくれるのは保護者の方々であることを念頭に、周囲にも気を配りましょう。
組体操の場合、先生が周りにいて、サポートやいざというときのために待機している場合があります。このような先生の邪魔にならないように気を付けましょう。
撮影しながらだと、なかなか難しい時もありますが、可能な限り子どもたちの安全には気を使いましょう。
最後に

いかがでしたか?最近の組体操は、危ない!危険!怪我があったらどうする!といった一部の保護者の意見から中止するか、開催しても限定された演技になることが多いような気がします。決めポーズにしても、本当に短い時間だったり、背筋や手先が伸びていなかったりで、いつシャッターを切っていいのか迷うこともあります。
その一方で、組体操に力を入れている幼稚園も多いような気がします。普段から体操の先生を中心に体操をはじめとする体育教育に力を入れていて、子どもたちも元気いっぱいです。
組体操には色々な意見がありますが、開催される場合には花形競技であることは間違いないと思います。カメラマンとして撮影に臨む場合は、気合を入れて、いい写真をとっていきたいと思います。






